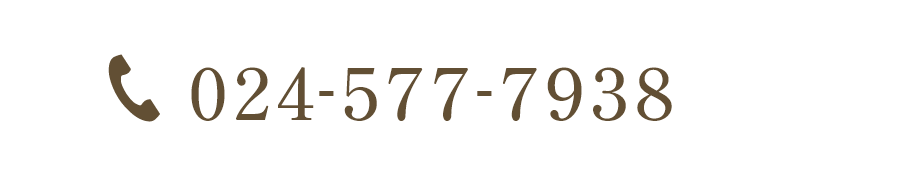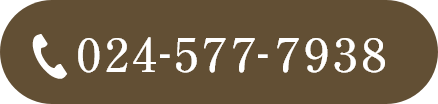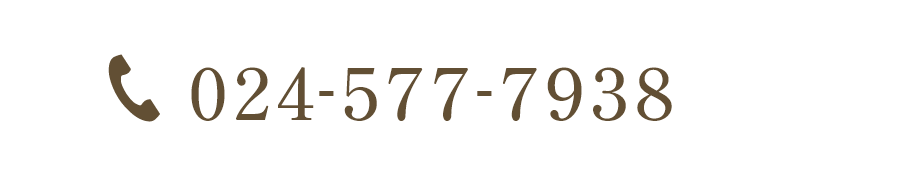インプラント治療期間の全貌~完了までにかかる期間と通院回数
目次 インプラント治療の期間はどのくらい?基本的な流れと目安 インプラント治療の通院回数はどのくらい? インプラント治療〜抜歯即時埋入法について インプラント治療中の歯のない期間はどうする? インプラント治療中の過ごし方と注意点 インプラント治療後のメンテナンスと長期的な経過 インプラント治療期間に関するよくある質問 まとめ インプラント治療の期間はどのくらい?基本的な流れと目安 インプラント治療は一般的に、初診から最終的な人工歯の装着まで3ヶ月〜1年程度かかります。この期間は個人の口腔内状態や治療内容によって大きく変わってきます。 当院では最新のシステムと技術を駆使して、できるだけ患者さんの負担を減らしながら、確実で長持ちするインプラント治療を提供しています。 インプラント治療の基本的な流れは以下のようになります。 工程 期間の目安 初診・検査 1〜2週間 治療計画の立案 1〜2週間 インプラント埋入手術 1日 治癒期間(骨との結合) 2〜6ヶ月 アバットメント装着 1日 上部構造(人工歯)の装着 1〜2週間 メンテナンス 定期的 特に治癒期間はインプラントと骨がしっかり結合するために必要な大切な時間です。この期間は上顎で約3〜6ヶ月、下顎で約2〜3ヶ月が一般的です。 インプラント治療の通院回数はどのくらい? インプラント治療の通院回数は、一般的に4〜8回程度です。ただし、骨の状態や治療内容によって変わってきます。 当院では患者さんの負担を考え、できるだけ通院回数を減らす工夫をしています。例えば、CTや口腔内スキャナーから得られたデータを活用したデジタル診断により、事前の計画を綿密に行うことで、無駄な通院を減らすことが可能です。 内容 通院回数 初診・カウンセリング 1回 検査・診断 1回 インプラント埋入手術 1回 術後チェック 1〜2回 アバットメント装着 1回 上部構造の型取りと装着 1〜2回 手術の内容や骨の状態によっては、さらに通院回数が増えることもあります。例えば、骨の量が少ない場合は骨造成が必要になり、追加の手術と通院が必要になることがあります。 私がこれまで経験してきた多くの症例では、患者さんの状態が良好であれば、5〜6回の通院で治療が完了することが多いです。当院では、オステムワンガイドを使用した精度の高い手術や、オステルIによるインプラント安定性測定を行うことで、治療の確実性を高めながら通院回数を減らす工夫をしています。 また、抜歯と同時にインプラントを埋入する「抜歯即時埋入」という方法を選択できる場合は、さらに通院回数を減らすことが可能です。 インプラント治療〜抜歯即時埋入法について 通常、抜歯後は骨が治るまで数ヶ月お待ちいただいてからインプラントを埋入しますが、条件が整っている場合は、抜歯当日にインプラントを埋め込むのが“抜歯即時埋入”です。この方法は従来よりも通院回数と治療期間の軽減が期待できます。 抜歯即時埋入 「その日」に、同じ処置のタイミングでインプラント体を埋入する方法のことです。池田歯科医院では、患者さまの口腔内条件をしっかり診断したうえで、この方法を選択できる場合があります。 (例)抜歯即時埋入の通院モデル(例) […]